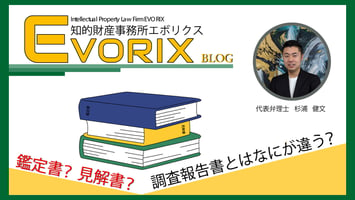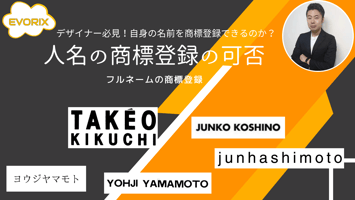前回の記事で、事業を開始する前に知的財産調査を行い、権利侵害のリスクを減らすことの重要性を解説しました。
知的財産権の侵害調査(FTO・クリアランス調査)の重要性とは?

ビジネスの現場では、特許調査(実用新案権調査)、意匠調査、商標調査など、さまざまな知的財産権の調査が行われます。これらの調査は、事業活動の中で自社が他社の権利を侵害していないかを確認するために不可欠です。特に、**「侵害調査」(FTO調査・クリアランス調査)**は、製品の開発・販売において重要なリスクマネジメントの一環となります。
なぜ侵害調査が必要なのか?
特許権、意匠権、商標権は、権利者が独占的に利用できる強い権利です。つまり、これらの権利が登録されると、権利者やライセンス契約を結んだ者以外は、その知的財産を使用することが禁止されます。
仮に他社の知的財産を知らずに使用してしまった場合でも、即座に権利侵害となる可能性があります。知らなかったでは済まされず、販売停止・損害賠償請求などのリスクに直面することになります。こうしたリスクを回避するために、事前に侵害調査を行い、安全にビジネスを展開することが求められます。
侵害の判断は誰が行うのか?
知的財産権の侵害が成立するかどうかは、各事業者ごとに個別に判断されます。
例:100円均一ショップと製造メーカーの場合
とある製造メーカーが100円ショップ向けに商品を供給し、100円ショップがその商品を販売したとします。もし、その商品が特許権を侵害していた場合、どのような結果になるでしょうか?
- 製造メーカー → 特許権侵害となる
- 100円ショップ(販売者) → 販売行為自体が特許権侵害となる
このように、特許権の侵害は、単に製造した企業だけでなく、販売する企業にも影響を及ぼします。したがって、製造メーカー・小売業者ともに、事前の知的財産権調査が不可欠です。
ECサイト・ネット販売における知財リスク
近年、Amazon・楽天などのECサイトが普及し、誰でも簡単に商品を販売できるようになりました。しかし、こうしたプラットフォームでは、第三者から「知的財産権の侵害」の通報があると、即座に出品停止・アカウント凍結といった措置が取られるケースが増えています。
この対応は、ECプラットフォーム自身が販売を継続すると、権利侵害者として訴えられる可能性があるためです。そのため、出品者は事前に十分な知財調査を行い、リスクを回避する必要があります。
また、製造メーカーや卸業者との取引においては、契約書で「第三者の知的財産権を侵害していないことを確認する義務」が求められることもあります。契約上のリスクも考慮し、慎重に対応しましょう。
知的財産権調査の実施と出願の活用
事業を安全に進めるためには、知的財産権の調査を積極的に実施することが重要です。
- 調査だけでリスクを回避できる場合
- 商標などは出願を行うことで特許庁の審査を利用する
商標権の場合、出願を通じて特許庁の審査を受けることで、一定の権利リスクを事前に確認できます。出願することで、低リスクで知財戦略を構築することも可能です。
契約書の落とし穴に注意!
契約書には、「第三者の知的財産権を侵害していないことを確認する」条項が入ることが一般的ですが、問題は**「保証する」**という文言が含まれる場合です。
知財侵害の有無は、最終的に裁判で決まるため、「侵害していないことを保証する」契約は極めてリスクが高いものになります。専門家の意見を参考に、慎重に契約を結ぶことが重要です。
知財調査・出願・契約書の確認は専門家に相談を!
知財戦略を適切に進めるためには、専門家のアドバイスが不可欠です。
- 特許・意匠・商標の侵害調査(FTO調査・クリアランス調査)
- 出願の可否判断や戦略的な知財活用
- 契約書のリスク確認・文言チェック
これらを総合的にサポートし、貴社の事業が安心して進められるよう支援いたします。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
.png?width=500&height=250&name=%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%82%A8%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%B9%20(500%20%C3%97%20250%20px).png)